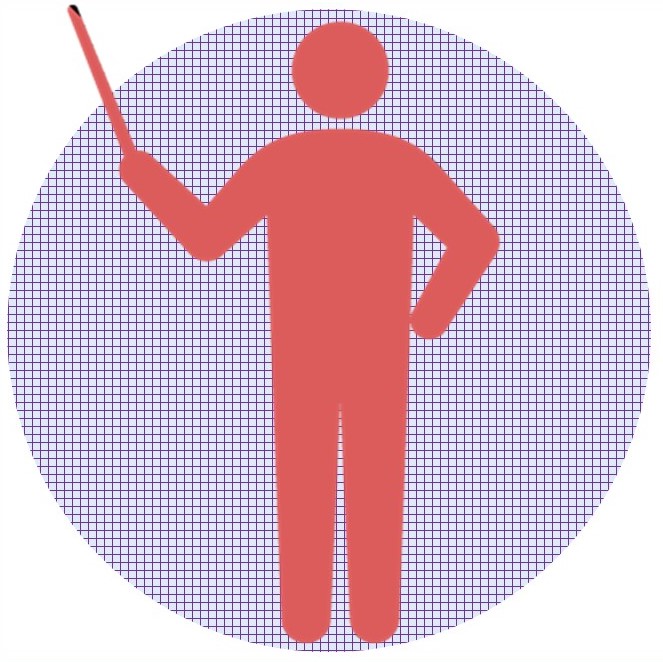
ルールを守るための仕組みを整えよう
- 組織の状況を把握し(要求事項4章)、目標を明確にし(5章)、リスクおよび機会に対する計画も決定したら(6章)、計画が実行できるように支援体制(人、設備、作業環境、教育機会など)を整えます。
- 組織活動をスムーズに行うためにルールを作っても、実際に守るのは困難。ルールを守らせる仕組みを作るヒントを知っておきましょう。
ルールを作るのは簡単、守るのは難しい
ルールを守るのも守らないのも「人」
ルールを守るための仕組みづくりは簡単です。
- ルールを決め(PLAN)
- ルールを守り(DO)
- ルールが守られているかどうかをチェックし(CHECK)
- ルールが守られていなければ改善、守られていればさらに改善すべき点を見つけていく(ACTION)
このようなシンプルなことが、ルールがうまくいくためのPDCAの仕組みです。
…と、言葉にすれば簡単ですが、実行するとなるとなかなか難しいのが現状です。
ルールを決めるのは「人」であり、ルールを守るのも「人」だからです。
機械やコンピューターであれば、命令を入力しさえすれば忠実にルールを守ってくれますが、従業員は機械ではありません。会社から従業員に対してルールを指示したとしても、ルールを守る人もいれば守らない人もいます。
ルールが守られない理由とは?
ルールが守られない、という現場では、以下のような声が聞かれます。

- 守りたくても守れなかった(事情あり)
- ルール自体が現場とあっていない(ルール不適切)
- ルールの必要性を感じない(ルール軽視)
- そんなもの守っていたら仕事にならない
- ちょっとくらいいいじゃないか
- ルールは理想、現実とは違う
「ルールを作り」「それを守る」という単純な仕組みも、実際にはそう簡単にはいきません。
ルールが守られなくても結果よければすべてよし?
「ルールが守られない」事例を紹介します。
結果が良ければルールを守らなくてもよい?
惣菜加工会社A社では、製造工程の中に原料を 「蒸す」作業があり、ルール(製品規格書)において「60~80℃で30分間蒸す」と定められています。
しかし、A社の実際の記録を見ると、温度は60~80℃のはずが「90℃」になっていたり、蒸し時間30分と定められているのに「15分」と記載されており、ルールが守られていないようです。
ところが、現場の責任者はこういいます。
「80度でも90℃でも商品自体にさほど影響はないんですよ。蒸し時間もあくまで目安ですから」
幸か不幸か?実際にこのまま出荷して、一度も問題が発生していないのです。
製造現場だけでなく、社会生活のあちこちでこのようなルール違反が見られます。
結果がよければ(商品に問題がなければ)ルールを守らなくてもよい…実際にこんな会社は多く見られます。
- 原料の厚みが微妙に違うから、その都度見てチェックしないといけない(からルール通りになどしていられない)
- 毎回こうしている(から今回もこれでいいはずだ)
このように明確な根拠なくルールを現場で無視するケースもあります。特に「決まり」よりも「経験」や「勘」で仕事する傾向にある現場では、ルールに従って同じ作業をすることに対し、抵抗を感じる人もいるようです。
ルールを守らなくても問題がないなら、「60~80℃で30分間蒸す」いうルールはそもそも必要ありません。
ルールを守るために
ルールには必ず理由があることを認識しよう
では、どうしてもルール通りにしなくてはいけないというなら、こうしたらどうでしょうか。

60~80℃で30分間と決めているから違反が出てくるのであって、基準を60~90℃で15~30分に変えれば、皆がルールを守れるじゃないか!
ルール改正をしてしまえば解決だ!
いえいえ、ここが「ルール」の怖いところです。
そもそもルールや手順書は何のために作るのでしょうか?
- みんなに同じ作業をさせるため
- ルールを外部の人に示すため
それも一つの目的です。
だからといって「みんなが守れるようなルールを作る」ことが、ルールの目的ではありません。
例えばサービス業なら「顧客の求めるもの」を提供するため、食品会社なら「消費者においしいもの、安全なものを届けるため」といった根本的な目標があるはずです。
規格やルールを決める際、何のためにこの作業をしているのかが、置き去りにされてしまうことがあります。
- なんのためにこの作業をするのか
- なぜこの温度、なぜこの時間で作業するのか
といった理由は必ずあるはずです。
まずは「ルールの意味を理解し、ルールを守ること」を徹底してください。
もしもルールの意味が不明確であったり、ルールが作られて時間が経ち、今の現状とは合わない状態になっていたら、「ルールを破る」のではなく、ルールを改正するようにしましょう。
仕事の目的を認識しよう
ルールは、実務で学ぶ「OJT」や研修などの「教育訓練」で身に付けていくのが一般的です。
しかし、教育を受ける側にそもそも「やる気」がない場合はどうすればよいでしょうか。
なかなか難しい問題ですが、「やる気」を出すための教育として、ひとつの事例を紹介します。
ルールを守る理由を「自分で」考えてみる
B社は清掃業やエアコンの洗浄作業なども行っている会社。B社では、ルールを守らせるための教育を行っても、なかなか従業員の意識が変わらず、ルールが守られないことが日常化していました。
そこで、「そもそもなぜ、エアコンの掃除が必要なのか」を、従業員に考えてもらいました。
- エアコンを洗浄する理由…熱交換率が向上するからでは?
- つまり、消費電力を削減することになるね。省エネってやつだ
- 省エネは「地球環境を良くする」ためにやるんだよね
- ということはつまり、私たちの仕事は「環境活動」じゃないのか?
- そうか! 単に「機械を掃除する仕事」ではない。地球の未来を守るための大きな使命を背負っているのだ!
エアコンの掃除は「きれいにする」ことだけが目的ではなく、結果的には「地球の未来を守る」という目的に行きついた、という例です。
どんな仕事にも、その仕事を行う「本当の理由」があります。
「なぜこの仕事をするのか」を理解することで、自分が毎日行っている仕事への認識も変わり、「やる気」が生まれまれるきかっかけにもなります。
作業をする人、作業を与える人、作業を管理する人、全員が「なぜ」を意識して「ルール」を守ることを意識していきましょう。

ISOは、トップダウンによる仕組みづくりという色合いが強いため、現場の人々は置いてきぼり、という印象を受けるケースも多いようです。
一方、組織で働く人々がそれぞれの業務が持つ意味や影響力、貢献度などを認識し、自覚することが大切だとされています。その認識や自覚が、人々に組織の一員としての意識を高め、「やる気」を生むことにもつながります。
単に定められた手順に従って業務を行うだけではなく、「やる気」を持って業務を行うことによって、持てる力を最大限に発揮することが期待できるのではないでしょうか。
最後に寓話「2人のレンガ職人」を紹介します。
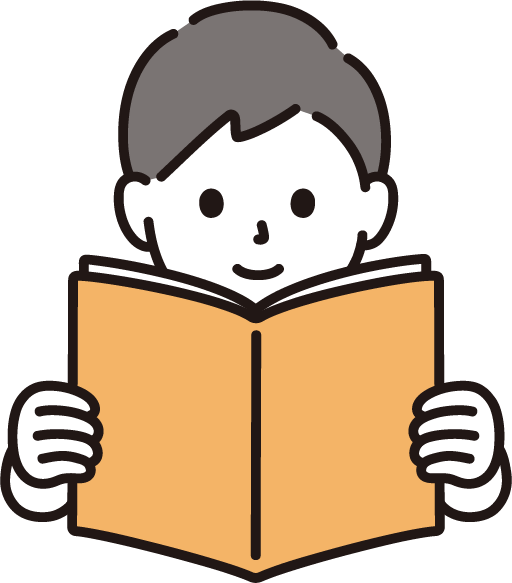
あるところに、2人のレンガ職人がいた。
「何をしているのかね」
と聞くと、一人の男は
「レンガを積んでいるのさ」と答えた。
もう一人の男は
「大聖堂を作っているんだよ」と答えた。
あなたはどちらのレンガ職人になりたいですか?
