7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化
組織に必要な文書を整えるために
- 組織の状況を把握し(要求事項4章)、目標を明確にし(5章)、リスクおよび機会に対する計画も決定したら(6章)、計画が実行できるように支援体制(人、設備、作業環境、教育機会など)を整えます。
- 文書化の目的、手順書以外の情報を共有化するための方法を理解し、組織に必要な文書を整えていきましょう。

文書化の目的とは誰かと「共有」すること
文書化の最大の目的は「共有」です。
文書とは、「今何らかの作業を行っている自分」と、「自分以外の誰か(未来の自分自身も含む)」とが「ある業務を同程度に理解できるようにする」ために情報を共有するものといえます。誰とも何も共有する必要がなければ、文書は必要ありません。
共有する相手は、組織の内部の人員だけではなく、第三者も含まれます。この場合の第三者とは、審査機関あるいは顧客です。組織に関する情報を共有するため、文書を整えておくことが推奨されています。
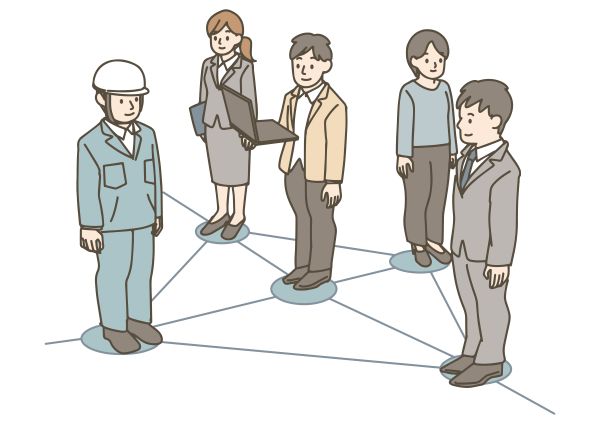
「形だけのISO」にならないために
とはいえ、文書とは審査のために作るもの、という解釈は正しくありません。
ISOシステムが誕生した当初は、ISO=文書化という認識もあり、審査に通るため、単にISO規格をそのまま組織の規格にしたマニュアルを作ったり、手順書や文書を山のように作って苦労した、というケースも多々ありました。
しかし、改訂を重ねるにつれ文書の必要性は少なくなり、2015年版では品質マニュアルの作成は必須ではなくなりました。
文書だけ、形だけのISOではなく、マネジメントシステムとしてきちんと「運用」することが重視されているためです。
ISOマネジメントシステムとは、個人のスキルやノウハウ、社員一人一人のベストプラクティス(最も良いやり方)を独りよがりにせず、会社としてのルールにして全員が実行することで、全体の効率を高めていくというものです。
ルールを作ったら、「こんなルールがある」ということを、誰にでもわかる形にする(見える化)ことが、文書化です。
ISOが要求する2種類の文書とは
すべてのスキルをノウハウにすること(文書化)は現実には不可能です。
ISOでは、以下の2種類の文書を要求しています。
- ISO規格が要求している文書
- システムの有効性のために必要であると「組織が決定した」文書
このうち、後者が優先されます。
すなわち、何でもかんでも文書を作るのではなく、何を文書化すべきかを自社で決めていくということです。
文書(手順書)が必要なのは、不適合管理、是正処置等の特定のルールに関してのみで、それ以外については、各組織の判断で、マネジメントする際に必要だと思うものを手順書や文書にすることが求められています。必要な文書だけに絞ることが可能だという解釈もできます。
つまり、
- 文書化しないと共有できないもの
- 文書化しなくても共有できるもの
これらを明確にし、(1)については文書化し、(2)については「何らかの形」で共有するようにします。
組織の中で、何が(1)で何が(2)なのか判断するのは難しいと思いますが、以下、いくつかのポイントを述べます。
文字がないと共有できないものを文書化する
まずは、「文書化しないと共有できないもの」について。
ノウハウを共有する
個々のノウハウを共有化し作業手順を明確にすることで、誰もが同じ手順で作業できるよう標準化、効率化が行われ、時間や作業工程のムダも省けるようになります。
そうすることによって、新入社員、派遣社員などが入ったときや、アルバイトやパート社員が多かったり、人の入れ替わりの激しい職場でも、短期間で他の社員と同様の作業を行えるようになります。
口頭だけでは伝わらないものを共有する
教育や周知活動で伝わらない部分について確実に共有化するためにも、文書はあったほうが良いでしょう。
文書にすることによって、曖昧なものを明確に形にして、皆で共有することができるのです。
例えば、弊社の所在地である福岡市では「燃えるゴミ」と書かれた指定袋があり、「燃えるゴミ」はその袋に入れて捨てることになっています。
燃えるゴミの回収日も指定され、啓発活動も行われていますから、「教育(周知)」を受けた市民はそのルールを守っています。
さて、このサイトは全国の方が読まれていると思いますが、福岡市以外にお住まいの方、「燃えるゴミ」とは、例えばどんなものかわかりますか?
いちいち書くと誌面がもったいないので、知りたい方は福岡市のホームページを見てください。
そこには「文字」で燃えるゴミのリストが掲載されています。
トラブルを共有する
過去に大きな事故があり、再発防止のためにルールや手順書が整えられるというケースもあります。
しかし、年月が経つうちにそのような事故は風化し、何のためにその手順書があるのか分からなくなることがあります。
業務と関わりがない文書は、無理に手順書として残す必要はありません。
しかし、それは果たして不要な文書なのでしょうか。
もともと従業員に周知すべき何らかの事由があって手順書を作ったのであれば、教育資料などとして活用する、といった方法もあります。
手順書という形での文書は必須ではありませんが、その代わりに新しい証拠となる資料が求められます。
教育資料も立派な文書の一つと言えるでしょう。
スリム化する前に「共有すべきもの」を考える
ISOシステムを運用するのに、あまりにも複雑なルールや膨大な手順書があると、作成するのも大変なうえ、うまく活用できず、ISOがお荷物になってしまうことがあります。このため「ISOをスリム化したい」と考える組織も多いようです。
しかしスリム化とは、「手順書の量を減らす」、あるいは「マニュアルの分量を減らす」ということだけではありません。
そもそもなぜ「不要」なものが存在しているのか。
文書をスリム化したいのであれば、量を減らす前に「何を共有したいのか」を考え、ISOをうまく活用するためのスリム化を行っていただきたいと思います。
ルールを共有化するための3つの方法
文書化を行う際、必ずしもマニュアルや手順書という形にする必要はありません。
全員が同じような考え方で取り組めるようにするための「何らかの方法」を決めることが大切です。
ここでは、組織のルールを共有化するための3つの方法をご紹介します。
①手順書を作る
一番手っ取り早いのは、やはり手順書や作業手順書などを作成することです。
手順書は、現場の作業の標準現場の最も良いやり方として作ります。手順書を活用し、全員がぶれない管理ができるようにします。
②見える化する
手順書まで作成していない場合でも、誰もがわかるような形式知(見える化)することも可能です。
文字に起こすことだけが標準化ではありません。目に見える形で識別を行い、どういったところに注意するか、それはどのように周知しているか等のルールを決めることも、立派な共有化です。
見える化の例
- 型や色、サイズなど、注意すべきポイントを太字で強調文字にする。
- 外国人の従業員が多い現場では、日本語は伝わりにくいため、間違えてはいけない部分(サイズ、グラム数、入り数など)を数字で周知する。
- 危険エリアと安全エリアは床の色を分ける。
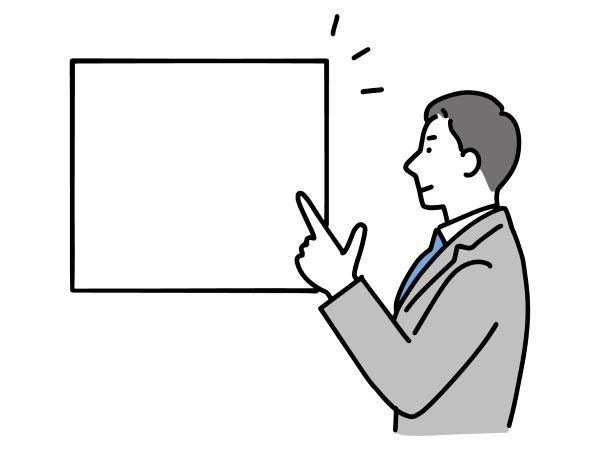
③暗黙の了解
文書は作成しておらず、暗黙の了解、阿吽の呼吸といったものでも、情報を共有化できているとみなされます。
例えば、朝礼等で伝えたり、日常の教育訓練等で従業員全体に十分ルールがいきわたり、全員理解している状態です。
手順書を作るべきか、「見える化」によって現場に周知しておけば十分なのか、人数も少ない場合などは、朝礼で適切に伝えておけば大丈夫なのか。
文書化の程度は、組織の規模や仕事の複雑さ、スタッフの力量などを踏まえて決めましょう。
ISO規格要求事項
- 4章 組織 4.1/2組織・利害関係者 | 4.3 適用範囲 | 4.4 プロセスアプローチ
- 5章 リーダーシップ 5.1/2 リーダーシップと品質方針 | 5.1.2 顧客重視 | 5.3 責任・権限
- 6章 リスク及び機会 6.1 リスク及び機会 | 6.2品質方針
- 7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化
- 8章 運用 8.1/2 運用・顧客とのコミュニケーション | 8.3 設計・開発
- 9章 評価 9.1 パフォーマンス評価 | 9.2(1) 内部監査 | 9.2(2) 内部監査の進め方
- 10章 改善 10.2 不適合と是正処置 | 10.3 継続的改善
